『プリティ・ウーマン』での戦略
1990年、映画『プリティ・ウーマン』の製作陣が、リチャード・ギアにどんな車を運転させようかと探していたとき、最初に声をかけたのはフェラーリとポルシェだったと語られています。
けれど両社は首を縦に振りません。
『娼婦を扱う映画にうちの車は出せない』――そう考えたからだそうです。
そこで白羽の矢が立ったのがロータス。
偶然のように巡ってきたそのチャンスが、やがて伝説を生むことになったのです。

この戦略はいまでも賛否が分かれます。
ですが私は、それはとても素晴らしい判断だったと思います。
なぜなら、単に市場シェアや売上規模でフェラーリやポルシェと競うことではなく、ロータス自身の立ち位置を明確に示していたと思うからです。
映画の本質は「愛」と「変化」
『プリティ・ウーマン』は娼婦を描いた映画ではありません。
本当のテーマは「真実の愛」「勇気」「人の弱さと優しさ」であり、人が互いに支え合うことで変化していく姿です。
リチャード・ギア演じるエドワードは、ジュリア・ロバーツ演じるビビアンと出会い、彼女を通じて自分自身の心にも変化が訪れます。
一方のビビアンもまた、エドワードとの関わりの中で、勇気をもって新しい自分に向き合っていきます。
二人は、互いに影響を与え合い、心を開き合うことで、共に成長していくのですね。
その変化の象徴として、ロータスはぴったりでした。
フェラーリやポルシェのような「定番」ではなく、どこか異彩を放つロータスだからこそ、映画の伝説化に貢献できたのかもしれません。
私にとってのロータスとの出会い
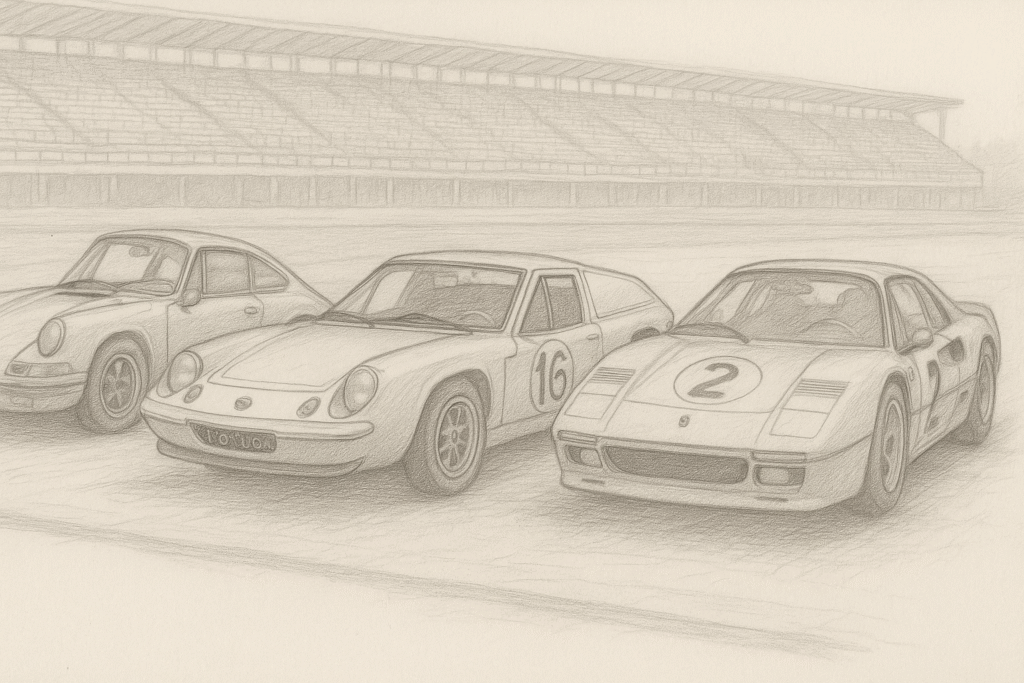
ただ、私にとってロータスの原点は『プリティ・ウーマン』ではありません。
もっと前の、子供の頃の体験です。
欧州ブランドに詳しい10歳年上の従兄弟が鉛筆で描いてくれたレーシングカーのイラストの中に、「ロータス・ヨーロッパ」がありました。
低く、平たく、未来的なフォルムは強烈でした。
映画のスクリーンではなく、紙の上の一枚の絵が、私にとってのロータスの始まりだったのです。
その記憶はいまも鮮明に残り、胸を熱くします。
ロータスの独自の立ち位置
フェラーリは「情熱と富の象徴」、ポルシェは「精密さと日常性」をブランドとして確立しました。
ではロータスは?
創業者コーリン・チャップマンの哲学「シンプルに、そして軽くせよ」が全てを物語っています。
ロータスは派手さや豪華さではなく、「走ることそのものの楽しさ」を提供するブランドでした。
軽量で俊敏、ドライバーとの一体感。
それがロータスが築いた独自の場所でした。
市場で支配的な存在ではなくても、熱狂的なファンに深く愛され続けたのです。
ブランドの真理
ロータスの物語は、ブランドにとって大切な真実を教えてくれます。
市場で一番大きくならなくても、人の心に一生残る印象を与えることができる。
売上やシェアだけでは測れない「記憶に刻まれる力」こそが、ブランドの本質ではないでしょうか?
私にとってのそれは、従兄弟が描いてくれたロータス・ヨーロッパの絵でした。
そして世界中の多くの人にとっては『プリティ・ウーマン』のエスプリかもしれません。
どちらにしても、ロータスは「忘れられない存在」として人々の心に刻まれています。
それがブランドの力なのだと思います。
